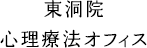以下のコラムは、京都いのちの電話ニュースレター第111号(2018年11月発行)に掲載された拙稿「僕の心にさわらないでくれ」を、転載したものです。
悩みを抱えた人の相談にのるとき、私たちはその人の心の弱い部分に触れることになる。しかしその人にとって、他者から心に触れられることは苦痛を伴う体験となる。医師から身体の傷を触れられることが、その傷を疼かせる体験になるのと同じように。
そうした他者に心を触れられることの苦しさが、筋ジストロフィーのために20才で亡くなった刈屋政人さんの詩に記されている。
あなたのそんな目はいやだ
僕の心の中まで見ぬくような目はいやだ
そんな目で
僕の心にさわらないでくれ
僕の心はほんとうに小さいのだ
そしてさみしくばかなのだ
そんな僕の心をあなたに見せたくない
見せたらあなたは僕から離れてゆくだろう
そしたら僕はどうしたらいいのだ
だから
ほっといてくれ
僕の心にさわらないでくれ
あなたのそんな目はいやだ
僕の心の中まで見ぬくようなそんな目は
(国立西多賀病院詩集編集委員会編(1975)『車椅子の青春―進行性筋ジストロフィー症者の訴え』p88-9)
刈屋さんが亡くなったのは、1971年のことである。しかし彼の言葉の切実さは、死後50年近くたった現代の私たちにも、心に触れられることがもたらす苦しさの実相を教えてくれる。
ここで重要な点は私たちが行う心理援助が、こうした苦しさを引き起こすことがある点だ。だから私たちも、刈屋さんが「あなた」に向けて発した言葉を、相談者から向けられることがある。
僕の心にさわらないでくれ――。
この言葉を前にして、私たち援助者はとまどう。その思いを尊重して、心に触れないほうが良いのか? 相談者が心を開くのを待つのがよいのか? それとも一歩、踏み出すべきなのか? 心理援助の過程を通じて、援助者はこうした問いに幾度となく直面する。とりわけ自殺予防の現場にいる援助者は、自殺をほのめかしつつも「ほっといてくれ」という言葉を発する相談者に出会う度、こうした問いに鋭く直面するはずだ。
そんな時、私たちはどうすればよいのか? そこに正しい答えは存在しない。ただ以下の点だけは、はっきり言える。援助者は自らの関与が相談者を苦しめる可能性があることを、常に自覚しておかなくてはならない。なぜなら、そのことを自覚しないで援助に臨んでしまえば、「さわらないでくれ」という思いの切実さを共感的に理解することができなくなってしまうからだ。