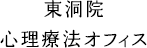以下のコラムは、京都いのちの電話ニュースレター第123号(2024年11月発行)に掲載された拙稿を、転載したものです。
自殺予防の現場で心理的支援を行うとき、知っておきたい言葉がある。「アタッチメント」という言葉だ。人間は心理的・身体的に危機的な状況に陥った際、誰かにくっつく、つまりアタッチすることによって安心を得ようとする傾向を有しているが、この傾向を説明する概念が「アタッチメント」だ。
このことを実感をもって理解するために、私たちの日常の一場面を想像してみよう。――たとえば、小さな子どもと久しぶりに親戚宅を訪れたとする。子どもは見慣れない親戚の顔を見て不安になり、父や母に身体を寄せる。しかし父母にくっついて安心できると、少しずつ親戚の問いかけに答えられるようになり、親の存在を支えにしながら、次第にその親戚と遊ぶことも可能になっていく――。こうした子どもの行動からも、人間には親しい人に接近して安心を得ようとする傾向があることと、その人を、いわば「安心の基地」にすることによって、新しい世界へと乗り出していけるようになることが理解できるだろう。
このアタッチメントに関して様々な研究が蓄積される中で、「安心基地」の存在が、健康な心を育てる上で決定的に重要な役割を果たすこと、そしてそうした基地の重要性は終生続くことが明らかになってきている。これらの知見は、自殺予防の現場で活動する私たちにも大切なことを教えてくれる。それは、当事者が安心して「死にたい」と言える場所を提供することの重要性だ。
現代において、自殺念慮を抱く人が「死にたい」とつぶやこうとする時、その場所としてSNSが選ばれることが多い。しかしそこは決して安全な場所ではない。批判や嘲笑の的になったり、場合によっては弱みにつけ込まれて搾取の対象になることもあるだろう。
だから私たち支援者は、当事者が安心して「死にたい」と語れる場所を用意する必要がある。この言葉を批判せずに受け止め、そうした思いを抱くに至った切実な苦しさを理解しようとする聴き手の存在は、当事者にとっての安心基地として作用し、当事者の心の中に生きていてもいいという思いを少しずつ育てることにつながるはずだからだ。
人間は、誰もが弱い存在だ。どんな人でも、苦しいことが重なれば、死にたい思いにかられてもおかしくない。そのことを踏まえれば、安心して「死にたい」と言える場所が社会の中に多数存在するようになることは、この社会が全ての人にとっての安心基地として作用するようになることを意味する。そうした努力の蓄積は、多くの人に生きづらさを感じさせている現代社会を、全ての人にとって生きやすい社会につくりかえていくための重要な一つの力として作用するはずだ。