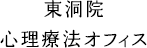以下のコラムは、京都いのちの電話ニュースレター第124号(2025年3月発行)に掲載された拙稿を、転載したものです。
近年、従業員に客から向けられる暴言やいやがらせ、迷惑行為などに対して、カスタマーハラスメントという言葉が広く用いられるようになってきた。そして、従業員の尊厳を踏みにじる、このハラスメントを無くすための努力が、社会の多くの場所で取り組まれるようになりつつある。
このハラスメントが特に深刻な問題となっているのは、対人援助の場面においてである。たとえば2023年に厚生労働省の委託によって実施された「職場のハラスメントに関する実態調査」では、過去3年間にカスタマーハラスメントを経験した人の割合が、医療福祉領域では53.9%だったと報告されており、これは他の業種に比べて明らかに高い頻度となっている。そして、こうしたハラスメントは従業員の心理に深刻な影響をもたらし、休職・離職を余儀なくされる人を発生させることも明らかとなっている。
こうした被害は、実は電話相談においても頻発している。たとえば性的な目的で話しかけてくる方や、威圧的な態度をとる方の電話を受けた経験のある相談員の数は多い。この問題が電話相談において特に深刻にとらえられなくてはならないのは、相談者の方の話を聴くとき、相談員は自分の心の弱い部分を開くことになるからだ。私たちが相談者の苦しさを本当に感じ取ろうとするためには、自らの心の弱い部分へアクセスしようとする。その瞬間に、突然性的な発言や威圧的な言葉をぶつけられると、相談員の心は深く傷ついてしまう。そしてその体験が繰り返されれば、心は次第に摩耗していくことになる。
もちろん相談員を守るために、いのちの電話もこの問題に対して対策を取ってはきている。しかし電話相談が匿名で行われ、それぞれが一回のみの相談であるという特徴が、有効な対策をとることを困難にしてもいる。
そこで読者の方々に、心に留めておいていただきたいことがある。それは、いのちの電話の相談員たちも、突然の性的な言葉に傷つき、威圧的な言動におびえる、弱い生身の人間だということだ。多くの悩める人たちの声に耳を澄ますためには、相談員の弱い心の部分がハラスメントによってもたらさられる傷つきから守られなければならない。そのことを皆さんに認識してもらえるだけでも、この問題にさらされている相談員にとっては大きな励ましとなる。