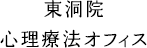最近ある障害者施設で、とても痛ましく、言語に絶する事件が起こりました。ほどなくして始まったリオデジャネイロ・オリンピックにかき消されて、あの事件は大々的には報道されなくなりましたが、私たちの外来に通院されている方の多くもまた強い衝撃を受け、消せない恐怖を訴えられていました。
私はある時期から「障害者」と「健常者」ということばにはある違和感をもつようになり、(たとえば○○さんは)「障害をもっている」という表現をするようになったので、普段は「障害者」ということばを使いません。私も老いてゆく中で、自然に不自由なことがらが増え、いろいろな「障害」をもつようになるのでしょうが、それでも今自分を「障害者である」と認識されている方にとっては、今回のような事件はたとえそれを実行した人がどのような人であったにせよ、私の想像することのできない根深い不安や不信・不安定感を与えるものであったであろうと思います。
私自身はこの報に触れて、私自身のある個人的な体験を思いました。
学生のころ私は、仲間としばらくの間ある施設で、介護のお手伝いの仕事をさせていただいていました。それは重い障害を持たれた入所者の方々が生活をしながら、医療サービスも受けることのできる場でした。お恥ずかしいことに学生になるまで、そうした重い障害を持った方の暮らしぶりに触れたことのなかった私は、学生になって仲間と見学をさせていただいたその施設で初めて入所者の方々に出会い、そうした重い障害をもって生きる人生があることを知りました。
私自身は平凡な医学生でしたが、ただ奇妙な違和感を抱えて生きていました。それは周りの生き物もまた人間も、つまるところ機械と同じからくり仕掛けではないのか、という疑念にまつわる違和感です。そうであるなら私たちが生まれてから死ぬまでのドタバタを、三度三度の食事を含めたさまざまの煩雑な手続きに耐えてくぐり抜ける意味はどこにあるのでしょう…?
それは当時の私にとっては、とても人には言えない、恐ろしい考えでした。けれどもそれは確実に私の中にあるものです。それがどれだけ恐ろしかったり、不遜であるかもしれない考えでも、自分が本当に心の底で感じていることをつかまえないで、あるいは言い当てないでいると、人間は結局はそのことに滅ぼされてしまう。今精神科医となった私はそのことを「知って」いますが、当時の私もどうしてか、そのことだけははっきりと悟っていました。ですので自分の抱えた奇妙な違和感についても、それを正確につかんで、できるなら言い当てておかなければ、結局はそれに巻き込まれやられてしまうだろうと、どこかで分かっていたのです。
そういうぼんやりした「宿題」の思いを抱えながら、私は毎日判で押したように、照りつける太陽の下を黙って歩いては施設に通いました。施設での仕事は当時の家庭教師の時給の何分の一かでしたが、見学に行った仲間のうち何人かが引き続きそこでのアルバイトを希望し、私と同じように照りつける太陽の下をやはり黙って歩いて施設に通っていました。
ある日のお昼時のことです。午前のプログラムが一段落して、いつものように入所者の方の食事が運ばれてきました。その日は七夕であったようで、配膳ワゴンの上には特別美しい盛り付けをされたお皿が並んでいました。(また別の機会にお話ししたいのですが、ここで働く調理師さんたちはほんとうに美しく、ひとつひとつの食事を整えていました。)それはおりひめ・ひこぼしの出逢う天の川をかたどったひやむぎで、一個一個星形にくり抜かれた西洋にんじんが、流れるように盛り付けられたひやむぎの上に飾られていました。
重い障害を持つ方は、座った姿勢を保つことや自分で食べ物を口に運ぶことが難しいので、介助者がスプーンを使ってお手伝いします。その日もお食事介助を担当する職員さんが、それぞれの入所者さんにお膳を運びました。私の近くに横たわっていた入所者さんの元にもお膳が運ばれ、担当の職員さんが入所者さんの体を起こしました。
私が衝撃を受けたのは次に起こった光景でした。職員さんはお皿を手に取り、入所者さんの目に映る位置に、その美しく盛られたひやむぎの天の川をさしだしました。しばらく一緒にその天の川を「きれいねぇ」と眺めてから、職員さんはおもむろにスプーンでその天の川をざくざくと崩し始めました(のどに詰まらせたりしないように、スプーンで刻んでから食べてもらうためです)。
介護施設の職員さんや、ご家族を介護されている方々には当然の光景でしょう。今の私にとっても、それはすでに当たり前の光景になっています。しかしお恥ずかしいことですが、当時学生であった私にとってこの光景は衝撃的なものでした。
美しい天の川を崩してしまう。ならば天の川なんていらないのではないか。最初からキザミ食として出してしまえばいいのではないか。
けれども私の食事はどうなのか。
美しい盛り付けやおいしそうな匂い、香り高いコーヒー・・・最後は咀嚼され嚥下されるものに、当然のように手をかけてもらっている。それが当たり前だと思っている。
ならば入所者さんが、天の川の盛り付けを楽しむことも当たり前だ。それは広い意味で文化と言ってよいものだろうけれど、文化というのはすべて意味がないと言えば意味がない。けれどもその重さは、私にとってと、入所者さんにとってと、きっかり同じなのだ。
人間に生きる意味があるかないかという問いにも、理詰めで納得できる答えにたどりつくことはできないかもしれない。けれどもここで暮らす入所者さんたちが生きている営み、職員さんたちが支えているここでの営みと、私の生きる営みとは、きっかり同じ重さなのだ・・・。
ことばでうまく表すことが難しいのですが、その頃から私に取り憑いていたあの問いは、もう自分から現れてこなくなりました。哲学的にはまったく答えにもならない「答え」でしょう。けれども私はその光景に出会ってから、生きることに意味があるかという問いの直接の解を得ることもなしに、「ただ生きる」ということができるようになったと思うのです。そしてその「ただ生きる」ということのために働く臨床医の仕事の価値についても、心から肯定できるようになったと思うのです。