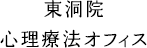とても素晴らしい本を読みました。
精神科医の夏苅郁子さんが執筆された『心病む母が遺してくれたもの-精神科医の回復への道のり』(2012年、日本評論社刊)という本です。
タイトルに「心病む母」と書かれているのは、著者が10才の時にお母さんが統合失調症を発病され、その後この病を終生抱えられることになったからです。そしてこの病はお母さんの精神を不安定にしただけでなく、娘である著者との関係も破壊し、さらに著者の心をも病的なものへと陥らせてしまいました。(著者は医学生の頃に拒食症になり、自殺未遂を二度おこしておられます。)
この本は、著者がその過程の中でどう苦しみ、どうやって乗り越えたかを、不都合なことを隠したり美化を施したりすることなく、できるかぎり率直に、正直に表現された半生史です。
著者にとってこの作品の執筆は、自分の過去の弱く愚かな部分をさらすことになるだけに、重大な覚悟を必要とする作業だったはずです。しかしそのような覚悟に裏打ちされた努力だったからこそ、本書には同じように弱く愚かな部分を有する私たちの心を動かす力が備わっています。
そうした力を有する特に印象深い一節を、ここで紹介しておきましょう。それは夏苅さんが医師になって四年目に、友人の助言を得て、お母さんと再会した時の一節です。お母さんの住む北海度で10年ぶりの再会を果たした夏苅さんは、お母さんの家に上がることになります。
寒さで震えている私を見て、母は「もっと、こっちへ寄ったら」と言って、ヒーターの傍に来るように手招きしました。
私は母の横にピッタリとくっついて座ることをためらっていました。すると、母は「お母さんのこと、気持ち悪いかい?」と聞いてきました。
この言葉を聞いて、私は泣き出しそうになりました。母にこんなことを言わせてしまったのは10年間も放っておいた自分なのだと、我が身を責めました。
母のこの言葉は、冬の北海道の凍てつく寒さの記憶とともに、母が亡くなった今でも、私の耳に残っています。(p77)
「お母さんのこと、気持ち悪いかい?」。この言葉を読んだ時、私は胸を衝かれるような思いがしました。統合失調症という病のために、お母さんは多くの人から幾度となく避けられたり、蔑まれてきたのでしょう。そうした体験が繰り返される中で、お母さんの中にこうした卑屈で悲しい自己意識が芽生えてしまった。その事実が、私にとてもやるせない思いを引き起こしたからです。
そして同時に、この言葉が著者にもたらしたであろう苦しみの深さにも、胸が塞がるような思いがしました。自分が母と断絶したことが、こうした母の自己認識を生む一因になった。そう気づいてしまえば、どうしても強烈な罪悪感に苛まれることになる。その罪悪感の深さを感じて、私はたまらない思いに襲われました。
こうした罪の意識の軛から私たちが自由になるには、そうした意識を消してしまったり、その重荷を誰かに背負わせるのでなく、自分が背負うべき重荷をちゃんと背負いながら、自分の足で立ち上がるしかない。そのことに気づいた著者は、最終的に自分の過去に向き合う道を選ばれました。そしてお母さんとの関係を振り返る中で、自分がいかに患者の話を聴いていなかったかということに気づき、それまで精神科医として「意識的に淡々と診療」していたのを、もっと患者さんの立場にたった診療態度に転換され、現在の夏苅さんは、「患者さんそれぞれの治るスピードを尊重する」(p74)こと、「患者さんや家族と同じ目線で考えてみる」(p101)ことを大切にして、自身の診療所を拠点に精神科臨床に従事しておられます。
このような夏苅さんの努力を読んで、私も強く励まされる思いがしました。というのは、私もこのオフィスの仕事を通じて、同様のことを大切にしたいと思っているからです。
つまり、自分の心の痛みにふれようとするクライエントの努力を援助しようとするのなら、まず治療者である私たち自身が、自分の不完全さや弱さを十分に自覚しておかなければならない。そして私たち治療者が、クライエントに問題を直面させのりこえさせようとするのでなく、あくまでクライエント自身が直面し、乗り越えていくお手伝いをしなくてはならない。
そのような努力の大切さを、この本を通じて夏苅さんにしっかり根拠づけていただいた気がします。もちろん夏苅さんほどの血のにじむような努力までには至りませんが、私なりの努力を積み重ねながら、当オフィスでの治療にあたれればと思っています。