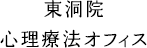一般に知られているように、日本は明治以降、足早な近代化を達成するために欧米の学問を急速に取り入れました。精神科医療も例外ではなく、ドイツ精神医学から臨床的概念を輸入し、それをもとに医療を展開してきたことは専門家の中ではよく知られた事実です。精神分析についても発祥の地であるヨーロッパから吸収され、当地の実践に活用されてきた歴史があります。
さて、そうした専門用語が作られた時代と現代の間には、相当な時間的・空間的へだたりがあります。それは本当に当時の意味内容を、そのまま保っているのでしょうか。その時代その場所で観察された「その現象」と、現代の私たちの前にある「この現象」とは、はたして同じものといえるのでしょうか。
もしかするとオリジナルの専門用語が生まれたそのときと、私たちがその用語をあたかも同じであるかのように口にするそのときでは、実は相当に換骨奪胎されていることもあるのかもしれません。
「行動化」
そもそも精神分析では、ふだん無意識的・自動的に行動に移されてしまうことを、あえて行動する前に意識してみることにより、十分に検討し熟考しようとする考え方があります。そのため患者さんには、治療の期間に何か行動に移したくなってもなるべく早急に行動に移さないという約束をしてもらいます。それでも我慢しきれず行動に移してしまうとき、そのことをさして「行動化」と呼んだのです。
けれども現代の精神科臨床の現場では、必ずしも精神分析的な考え方を取り入れているのではない場でも、周囲の人びとにとって「困った」行動が、しばしば「行動化」と呼ばれています。患者さん自身の身体や生命が危機にさらされるような行動はもちろん「困った」行動といえるでしょうが、実際にはそれ以外に、周囲の手を患わせる可能性がある行動もまた「困った」行動とされているのではないでしょうか。健常者には許されている人生の試行錯誤が、なぜ今その患者さんには許されないのか、私たち援助者は時に立ち止まって考えてみなければならないと思います。
「ケース」
これはもともと治療者と患者とが一緒に治療の道程を進んでいく、その一回性の物語の運びゆきを指して用いられていた言葉です。けれども今の臨床現場では、患者さんその人を指して「事例」とか「ケース」というようにしばしば使われています。そうした呼び方で呼ばれるとき、その患者さんは援助者から切り離され、相当に対象化されています。冷静な判断を要するなど、それが治療上必要な理由もあるかもしれません。けれども援助者自身が患者さんとの情緒的な結びつきを苦しく思っているとき、患者さんの存在をモノ化する働きも、この言葉には込められていないでしょうか。少なくともそういう可能性があることを忘れないようにしたいと、自戒を込めて思います。
英国の精神分析家ウィルフレッド・ビオンの業績に、「グリッドgrid」という図表があります。これは「同じ言葉でも、その抽象度の水準(縦軸)や、それが用いられる目的(横軸)とは、それが使われる場面によって違う」という発想を伝えています。上に述べた「換骨奪胎」も、同じ字づらや音韻をもつ言葉が、ビオンのいうグリッドの横軸のちがいでさまざまに用いられているのだと考えれば納得がゆきます。言葉は字づらが同じでも、そのコミュニケーション場面でどう使われているか、何のために使われているかによって、同じではないのです。
ビオンは言葉の陳腐化・換骨奪胎化という現象をよく知っていたとみえて、至る所で既成の専門用語でなく、なるべく意味の手垢のついていない単語(もっと極端な場合は記号)をもってきて、それに自分の指し示す意味内容を担わせ、自分の伝えたいことを、なるべく正確に読者に伝えようとしていました。私たちが経験上知っているように、言葉の換骨奪胎化は非常なスピードで進みます。その点でビオンは賢明であったといえるのかもしれません。