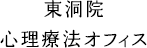以下のコラムは、京都いのちの電話ニュースレター第106号(2016年3月発行)に掲載された拙稿「苦しむべきことを苦しむ」を、改題して転載したものです。
精神科医として患者の援助にあたっていると、患者のおかれた状況のあまりの厳しさゆえに治療的希望を見失いそうになることもある。しかしそんなときに、勇気と励ましを与えてくれる言葉がある。それは宮沢賢治が知人に送った手紙の次の一節だ。「どうか今のご生活を大切にお護り下さい。上のそらでなしに、しっかり落ちついて、一時の感激や興奮を避け、楽しめるものは楽しみ、苦しまなければならないものは苦しんで生きて行きませう」。
この一節は賢治が死の10日前に書いたものだ。彼はこの言葉を書くまでに、多くの苦しみを経験した。信仰上の対立から生じた親友との離別、最大の理解者だった妹トシとの死別、農業の発展を願ってとりくんだ啓蒙活動の行き詰まり、肋膜炎によって差し込んできた死の影……。それらがもたらす不安や悲しみを経験した果てに、彼はこの言葉を綴るに至った。
彼の体験した苦しみの多くは、医学が進歩し、社会制度の発展した現代においては体験せずにすむものとなっている。しかし、それでもなお私たちの人生には苦しみがつきまとう。人間関係での傷つき、親しい人との別れ、経済的不安、そして病気や死。そのように避けがたく訪れる苦しみに対して、賢治は「苦しむべきことを苦しむ」よう勧めている。
なぜなのか。彼はその理由を記してはいないが、彼が残した作品から推測するに以下の二つの理由があるからだろう。一つは、苦しさを深く経験することによって、他者の苦しさを理解しやすくなり、異なる立場の人たちと共生できる可能性が高まるということ。そしてもう一つは、苦しさを深く知っているからこそ、日常の中にひそむ小さな喜びや美しさの価値を玩味できるようになること。
この推測を裏づけてくれる作品の一つに、妹トシとの死別を描いた『永訣の朝』がある。トシは死の間際に、「そらからおちた雪のさいごのひとわん」を賢治に所望する。彼は表に出て雪をすくいつつ、それが「天上のアイスクリーム」となり、「おまえとみんなとに聖い資糧」となってもたらされるように祈る。トシとの魂の交流を哀切に描き出す彼のことばを通じて、私たちはみぞれまじりの雪でさえも、人間を人間らしくしてくれる美しさと悲しみに満ちた物質であることを知る。
この作品だけでなく、彼はつねに苦悩の中から作品を生み出していた。そうした作品群を読む中で私たちは、あたりまえの日常の中にも潜んでいる生の喜びや自然の美しさの存在を確信する。そしてその確信を深くすることができれば、たとえ私たち自身が圧倒的な困難に直面しても、それを生き抜くこと自体に意義があると思えるだろうし、また援助者として絶望的な状況にある患者を前にしても、彼もいずれは苦悩の向こう側に希望を発見するはずだと信じつづけることができるだろう。
そのような意味において冒頭の賢治の言葉は、困難な患者の治療にあたる時だけでなく、人間的な価値を大切にしながらこの世界を生きるために必要な勇気を与えてくれる。ただ-それは確かだけれど-、この彼の励ましを受け取るだけの覚悟を、援助者としての私たちは本当に抱くことができるだろうか?