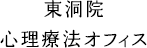「情動失禁」ということば
私が病院で入院患者さんについての精神科的相談を受ける仕事をしていた頃、病棟でよく耳にした言葉がありました。「情動失禁」という言葉です。看護や介護に関わる方ならご存じかと思いますが、これは本来的には「わずかな刺激で泣いたり笑ったり怒ったりする状態で、情動の調整がうまくゆかない」(注1)状態とされ、認知症や脳梗塞後の患者さんなどに見られる症状とされているものです。精神科の相談業務をする際には、その患者さんが日常どんな場面でどんな言動をされていたかを具体的に知る必要があるため、まずは患者さんの最も身近で働いている看護師さんの記録を読んでゆくのですが、その中にこの「情動失禁」という用語がしばしば使われていたのでした。
脳梗塞や認知症の患者さんかなと思ってカルテを見てもそうではなかったり、前後の文脈から、怒って拒否をしたり涙を流しても不思議ない状況があったり…。要するに、怒っておられた・泣いておられたという記載でよいのではと思う場面にも、「情動失禁」という専門用語があてられていたのです。
そういう時は看護師さんに直接状況を確認するように努めましたが(とはいえ交代勤務なのでなかなかその時の看護師さんに会えないことも多いのですが)、やはり状況からして自然な感情を表しただけと思われる場面でも、しばしばこの用語は使われていました。その都度、精神科医がわざわざ説明する奇妙さに戸惑いつつも「状況からいって、患者さんのその反応は自然であり、特別な身体や精神の病気が原因とは考えられない」という趣旨の報告を書くしかなかったのでした。
最初のうち私はこのことについて、看護師さん個人の資質や感受性の問題として片付けがちでしたが、何年にもわたって繰り返しこの現象に出会い続けるうちに、それがどういう事情から起こってくるのか考えるようになりました。そこで思い至ったのは、病院という場所が看護師さんたちにとって(そしておそらくわれわれ医者を含め医療スタッフ皆にとって)相当に感情を揺さぶられる場であり、ことによっては慢性的にトラウマを受け続ける結果、「燃え尽き」に陥りかねない現場であることでした。
看護師さんたちは日々、突然運び込まれてくるさまざまな事情を抱えた患者さんのお世話をしています。そうした患者さんたちの多くは、突然生じた身体の不調に驚き、その一番大変なときに慣れ親しんだ家や家族を離れて、病院という見知らぬ世界に放り込まれ、時には必要性を理解できない検査を次々に受けねばなりません。中でも障害が残る状態で退院せねばならなくなった人の多くは、思い描いていた自分の運命が変えられてしまった事実に直面し、嘆きに暮れます。しかも病院は限られたリソースを多くの人たちに配分せねばならず、保険医療の範囲で行えることには限りがあるため、そうした悲嘆のさなかにある人をそのまま退院させねばならないこともしばしばです。それを一番身近にいる看護師さんたちは、日々目撃し続けねばならないのでした。
「情動失禁」という専門用語を使って、人間的な悲嘆を一症状へと落とし込むことは、職業的に悲しみの洪水をあびねばならない立場に置かれた看護師さんたちが、自分の心身を守るために編み出した、一つの防御策だったのではないでしょうか。
悲しみは「病気」?
精神疾患の診断基準としてアメリカ精神医学会が作成している「DSM」という出版物があります。2013年にその最新版である「DSM-5」が出版されましたが、その編集段階では、親しい人を亡くした悲しみと病気としてのうつ病を区別する線引きが曖昧化するかのような改定案が出されていました。そのため、人間として自然な悲しみまでも「病気」にされてしまうのではないかと、精神科医ばかりでなく一般人を含め多くの論者の間で論争が巻き起こりました。最終的には”Major Depressive Disorder”(おおよそ病気としての「うつ病」診断に相当します)の診断基準には、医師による慎重な鑑別を要する旨が記され、病気としてのうつ病と自然な悲しみの鑑別ポイントが注として付記されるという結論に落ち着いています(注2)。
人間として自然な感情としての悲しみを「病気」として治療の対象にしてしまうことへの危惧は、他にも表明されています。精神神経学会は日本の精神科医の多くが属する代表的学会ですが、その学会誌に「うつ病臨床における『えせ契約』(Bogus contract)について」というタイトルで発表された井原裕先生の論文(注3)もその一つでしょう。その中で氏は、本来人間的な悩みの領域にある問題までも医療で解決できるかのような前提で暗黙裏に結ばれる治療契約を、「えせ契約」という強い言葉で批判しています。学術誌に掲載される論文としてはかなり強いこの表現が、こうした状況に対する危機感を伝えていると思います。
病気ではない「悩み」・「悲しみ」をそれとして認めること
1977年ジョージ・エンゲルが提唱した「バイオ・サイコ・ソーシャルモデル」には、精神科を含め医療が出会う問題は脳の病気など身体的・生物学的な次元の問題(「バイオ」的な次元)ばかりでなく、人が他の人間と関わり合いながら生きている中で生じてくる社会的・心理的な悩みの次元(「サイコ・ソーシャル」な次元)があることが示されています(注4)。
脳腫瘍による幻覚症状や、お薬が効くことが分かっているてんかん症状・典型的なうつ病など、現代医学による治療が一定有効なことが分かっている状態に対しては、もちろん有効な医療的手段をとることが第一です。逆に確たる理由もなくその手段を取らせないことは、非合理的であるばかりでなく非人間的でもあるでしょう。けれども人間としての悩み・悲しみまで、薬などの手段で「治療」しようとすることはどうでしょうか?
「感情失禁」の例に戻りましょう。冒頭でも申し上げたように、入院中の患者さんが涙すること・怒ることを人間として自然な感情と認めることは、医療従事者にとっても大変つらいことです。医学的な症状の一つであるかのように「感情失禁」とラベリングして精神科医に対応を求めることも、あるいはそうした気持ちからの行動かもしれません。しかし、それがもし身のまわりの出来事に対する患者さんの悲しみや怒り、すなわち人間としての自然な感情であったら…? また、そこでもし対応を求められた精神科医が「『症状』に対する『治療』を」と、薬を処方してしまったら…? たいていの場合、それは誤った対処であるがゆえに効果も少なく、たとえ何らかの「効果」があったとしても、相当に非人間的なことではないでしょうか。
たとえ善意から発した対応であったとしてもわれわれ精神科医は、人間としての悲しみや悩みまでも病気の枠に押し込めて、薬で治療しようとしてはならないと強く思います。
精神科医の仕事はまず、その方の抱えている困難について、それが主として体や脳のレベルの問題なのか、人間としての悩みのレベルの問題なのか、あるいはその両方がどの程度・どのように絡み合い困難を引き起こしているのかを、的確に見立てることです。そして病気には病気としての手当をなした上で、それでもまだ残る悲しみは悲しみとして受け止め、その語りに耳を傾けることではないでしょうか。
(注1)
新版精神医学事典. 弘文堂, 1993.
(注2)
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. American Psychiatric Association, 2013.
(注3)
井原裕 うつ病臨床における「えせ契約」(Bogus contract)について. 精神神経学雑誌, 112: 1084-1090, 2010.
(注4)
Engel G The clinical appplication of the biopsychosocial model. American Journal of Psychiatry, 137: 535-544, 1980.