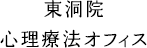私は普段、市中一般病院で働いている一精神科医である。
以前、この病院を辞めて出て行くことになったある医師にお別れの挨拶をしたところ、「私ももうしばらくここでがまんしていられたらよかったのですけれど…」と言われたことがあった。我慢? 私は今、ここで働きながら「我慢」をしているのだろうかと私は心の中で自問した。医学系の研究職に就くために出て行くその人は、これまでがまんしてここで働いていたのかもしれなかった。
そのときから私は、臨床と研究ということについて立ち止まって考えるようになった。
他の市中病院もそうだと思うが、私の病院にもたくさんの看護師さんたちが働いている(いわゆるコメディカル・スタッフと言われてきた人たちも含め)。その中には研究をしながら臨床に携わっている人もいるかもしれないが、多くの看護師さんたちは自分の家庭にもそれなりの密やかな困り事を抱えながら、担当患者さんが熱発しただの、痰詰まりを起こしたのという日々の必要に迫られて、病棟内を走り回っている。「研究」するゆとりを持てている人は一握りかもしれない。いや、ゆとり云々というよりそもそもそこに重心を置いていない。看護師さんたちを動かしているのは、もっと別の何かだという気がした。
森鴎外の短編『カズイスチカ』(1911)には、親子2世代の医師の日常が描かれている。父親医師は一人ひとりの患者を相手に昔ながらの診療を黙々と続けているが、息子は明治以降の(おそらくは科学的な)医学を学んだ世代である。
「翁は病人を見ている間は、全幅の精神を以て病人を見ている。そしてその病人が軽かろうが重かろうが、鼻風であろうが必死の病だろうが、同じ態度でこれに接している。」
「花房学士は何かしたい事もしくはするはずの事があって、それをせずにしばらく病人を見ているという心持である。それだから、同じ病人を見ても、平凡な病だとつまらなく思う。Interessantの病症でなくては飽き足らなく思う。」
翁は父親、花房学士は息子であるが、この二人が仕事に当たるさまは非常に違う。外から見れば同じかもしれないが、内面は相当に違っている。父親が臨床家の心であるとすれば、息子は科学者の心といえるかもしれない。
科学者の心には、目の前の患者は退屈である。どれもこれもありふれた事象で、何一つ新しいことは起こらない。医科学者である息子は、いわば新しいものを探す目で患者の群れを見ている。
臨床家の父親はどうか。事象が新しい・新しくないということで患者を選別していない。もっと言うなら患者と過ごす時間を、都度新しい機会としてとらえているようにも見える。
科学の世界では、新しいこと・知られていないことの発見にこそ価値がある。たいていの事象は「同じこと」の繰り返しであるから、それに接する者はそれを「処理する」だけということになる。ありふれた市中病院は退屈な場所で、せいぜい新しい発見につながる事象を目をこらして見つける努力をするしかない「がまん」の場ということになる。
けれども臨床家の心は、新しいかどうかをそもそも問題にしていない。『カズイスチカ』の父親医師も、病棟を日々駆け回る看護師たちも明らかに、事象の新しさに惹かれてこれに関わっているのではない。彼らを惹きつけているものはもっと別のものだ。
すぐれた看護師さんたちを見ていると、彼らが勝負しているのは「新しいこと・知られていないことの発見」という領野ではなく、「言い古されたこと・知られているはずのことの実践」というまったく別の領野であることが分かる。彼らは毎回真剣である。事象を「処理」していない。
科学的な価値の世界から見れば一般市中病院はありふれた疾患の集まる退屈な場であるかもしれないが、臨床的価値の世界では、そこは最前線なのだ。
臨床的な価値の世界は、「新しいことをより多く」知ることではなくて、「言い古されたことをより深く」知ることが問題にされる世界だ。そこでは頭でそれと知っているだけではなく、そのことのさまざまな意味合いを、情緒的な陰影も含めて深く感じ取ろうとする心が働いている。精神分析家ネヴィル・シミントンはものごとのそういう知り方を、「活きた知にすること(vital realization)」と呼んだ(注1)。すぐれた看護師たちの真剣な仕事は、ここで勝負している。
(注1)
Neville Symington(1994) Emotion and Spirit. London, Karnac Books.
(『精神分析とスピリチュアリティ』ネヴィル・シミントン著、成田善弘監訳、北村婦美・北村隆人訳、創元社、2008)