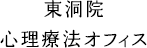仕事柄、子どもをもつ母親の立場にある女性たちの話を多く聴いてきた。
母親である人がある時に、個人としての生に立ち戻ろうとする衝動を自分のうちに強く感じ、それが家族や子どもに及ぼす影響を思ってみずから恐れ、悩む局面というものがあると思う。たいていは基本的に非常にまじめな人であり、母親として子どもを何とか守り育てたいと、強い使命感を感じて母親役割をがむしゃらに務めてきた人に多い。そうした人の中に突然異物のように、個人としてこれまで極めきれないでいた、やり残した何かに向かっての強い衝動が現れるのである。
「個人」としての生、というと、普通はよいこと・望ましいことのように思われるかもしれない。けれども幼い子どもにとっては、母親が自分と直接関係のない意思を持った「個人」として立ち現れることは、かなりの場合恐ろしいことでありうる。たとえばウィニコットという精神分析家は、幼い子どもにとって母親が空気のような存在となって欲求をちょうどよいタイミングで満たしてくれ、一定期間万能感を維持してくれることが、健康な精神的基礎を形作る上で大変重要な条件になると考えていた。だから母親が個人として「こうしたい」という意思をあまり突然に出してくることは、子どもにとって精神的な外傷になるのである。このことは私にとっても臨床的な経験にてらして、たしかに納得されることであった。
家庭は子どもにとって、文字通り命をはぐくむ場所であるし、また他の家族成員にとってもいわば命を毎日更新する場所である。一般に家庭はプライベートな空間だということになっているが、その家庭という場を整えることは母親にとって「仕事」であり、母親たちは多かれ少なかれ、その責任の重さを自分の肩の上に感じながら暮らしている。こういう仕事をしていくことは、母親となった人にとっていわば「個」を抑えて、初めて成り立つ面をもたざるをえないのである。
こうした悩みを聴くとき私たちセラピストは、いわば捨てられる子どもの側に身を重ねて、母親の側を義務の放擲者と見ていることが多い。これは職業柄人間の心の発達ということを学ぶ中で、母親を「支え手」として、もっというと脇役として見る習慣からくるものであろう。この場合セラピストは、その来談者を母親としてだけ見ている。
あるいは女性の権利ということを強く押し出す考えを持ったセラピストであれば、逆に母親が個人としての自覚を持って「羽ばたく」ことを、個の成長とみて鼓舞し後押しするかもしれない。この場合はセラピストは、いわばその人を本来的に個人として見ている。
けれどもセラピストとして聴くわれわれに必要なことは、母親としてのその人と、個人としてのその人の、どちらかだけをその人のあるべき道筋と思いなして、他方の存在を無視したり圧殺したりしないことである。実際、セラピストがそのどちらかをその人のあるべき姿・完成形として思い描きつつ聴いているとき、心理療法はしばしば中断してしまう。
母親としてあるということと、個人としての可能性を伸ばしていくということは、ほんとうは人間にとってどちらかに還元し切ることのできない、2つの大きな原理に根ざしている。およそ人間が出会う判断というものは、この2つのバランスをどうとるかということにかかっているし、また人間の人となりというものも、この2つのあいだでその人がどういう判断をつけるかということの中に表現されると言ってもよいくらいだ。母親としての生か、個人としての生かというこの母親たちの卑近にみえる悩みは、この普遍的な問いが生活の断面に端的な形を取って現れ出たものといってよい。
この悩みを悩む人は、人間にとってもっとも根本的な2原理のあいだでどう立つかということに悩んでいるのだ。請け合って言うが、それは悩むに足る悩みである。