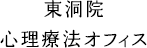専門書ではないのに、読み返すたびにいつも新鮮な気づきを与えてもらえる本があります。津守房江さんの『育てるものの日常』(婦人之友社、1988)です。
著者紹介によると、津守房江さんは1930年のお生まれで、お茶の水女子大学家政学部児童学科を卒業され、日本保育学会の会員であられたとのことです。やはり教育や保育を専門とされていた夫の津守真さんとのあいだに4人のお子さんをもうけられ、本書にはその家庭生活から気づかれた、さまざまなことが語られています(以下、夫の真さんと区別するために「房江さん」という呼称を使わせていただきます)。
本書を開くと、子育てに追われる忙しい日常の中で、房江さんが子どもさんたちをそっと見守っておられた様子が伝わってきます。「これで分かった」というキリをつけてしまうことなく、完全な答えは出なくても、房江さんは子どもさんたちの何気ないしぐさやことば・やりとりに気持ちを向け、そこに込められているかもしれない大切な「意味」を思い続けておられます。
本書の冒頭部分からの引用です。
子どもと生きる日常は、小さな出来事の連続である。子どもの食物を作り、体を洗い、服を着せ、その間に子どもたちのぶつかり合いがおきる。今日一日何をしたのか、思い返しても、取り上げるほどのこともない小さな出来事ばかりである。私は「まるで砂を握りしめたよう」 という思いに取りつかれる。砂は指の間から、ぱらぱらとこぼれ落ちて、何も形を成さない。あんなに働き、心を緊張させることもあったのに、こぼれ落ちる砂のように、とらえどころのない、この日常の生活。この中から抜け出さずに、この現実を生きることの重さを感じる。
だが「待って」と自分に働きかけるもう一人の私がいる。この中で子どもは確かに育っている。手の中からこぼれる砂のようでも、その中で子どもたちが育っていくなら、その砂の一つぶ一つぶは、大切なものを含んでいるのではないか。日常の出来事の一つ一つを大切に見てみよう。大切に考えてみよう。それが子どもと日常の生活を生きている、私のテーマなのだと思う。その思いが私を活気づかせ、楽しんで子どもと生きるように、心を向けるようになった。(p.1-2)
ここで房江さんは子育てについて語っておられますが、精神科医の私は、日々患者さんの変化を間近に見せていただく臨床の仕事をしています。治療者の肩書きによらず、今ここでの個別の偶然にどのような必然の意味が含まれているかを細やかに感じ取ろうとしつつ、日々の面接を重ねている同業者の方を見かけると、私は自然に頭が下がります。そういう方から学び、自分もそのようになりたいと思うからです。
「その砂の一つぶ一つぶは、大切なものを含んでいるのではないか」。
房江さんの本を読んでいると、確立され固定化した教条として精神医学や心理学をもちいて事象を「切る」という、ともすれば臨床家が陥る可能性のある態度から自由になり、素朴ではあるものの臨床家にとって決定的に大切なあり方へと引き戻されるような思いがします。それが未熟な自分にはまだまだ必要だからこそ、私は何度も房江さんの本を手に取りたくなるのでしょう。